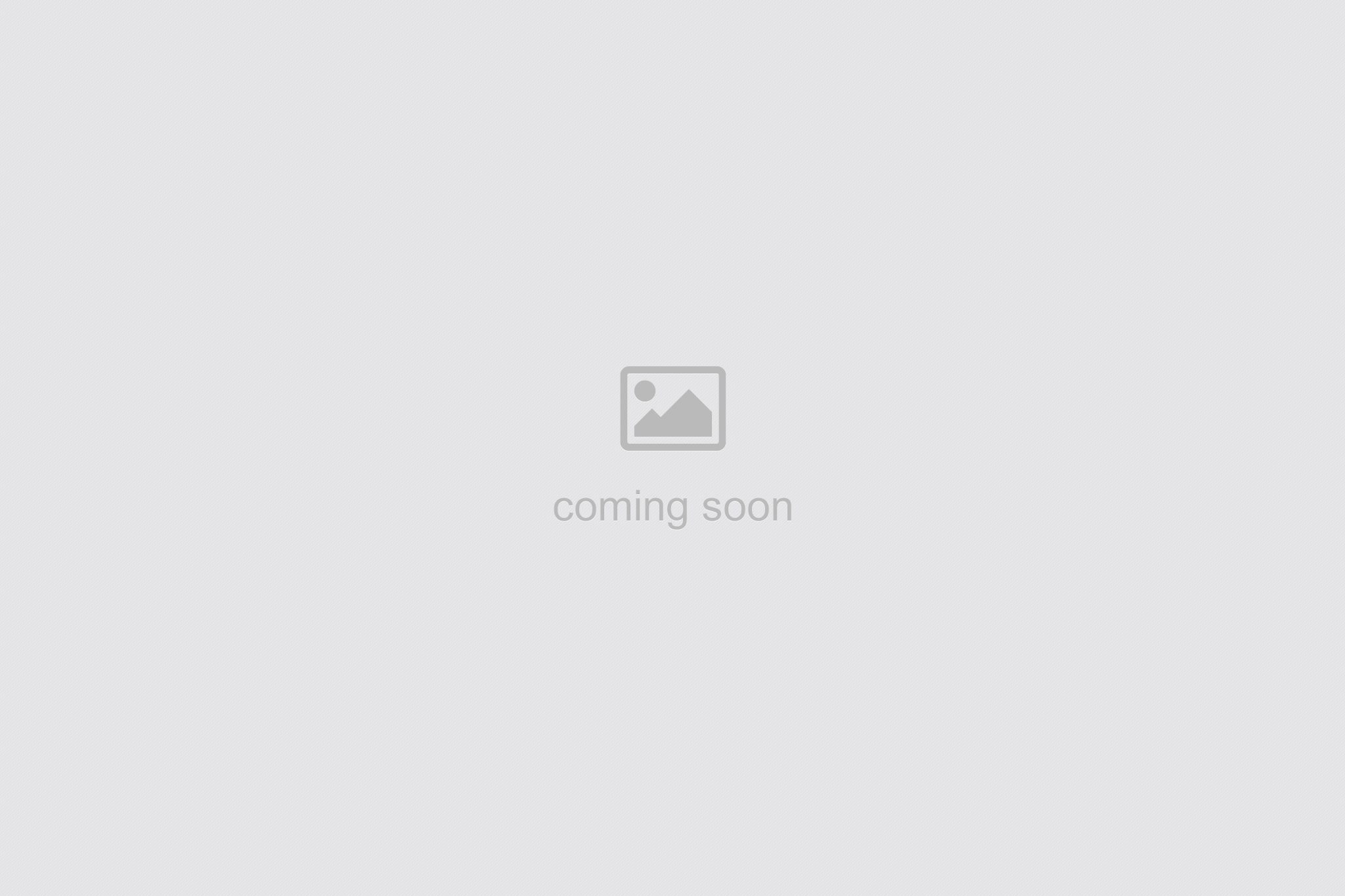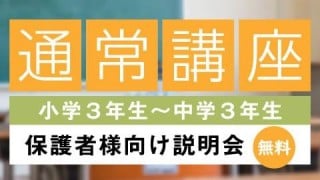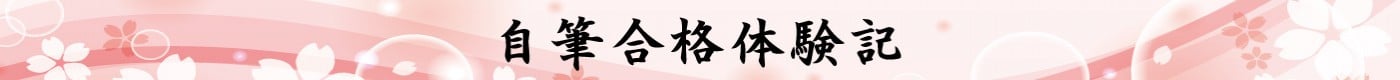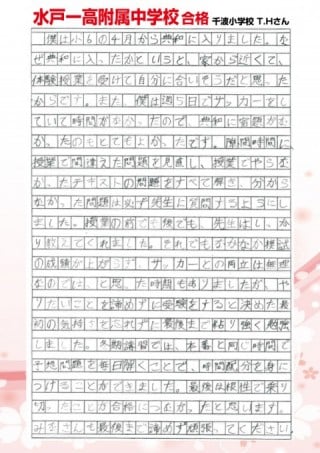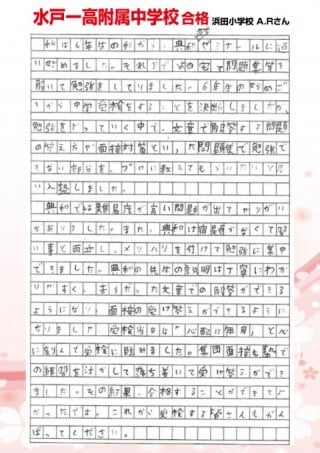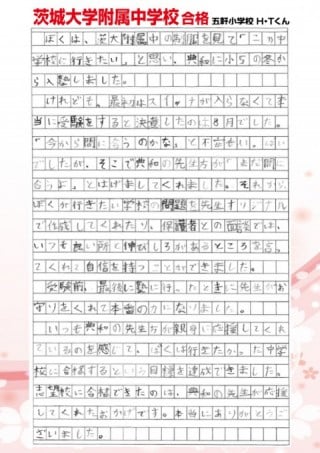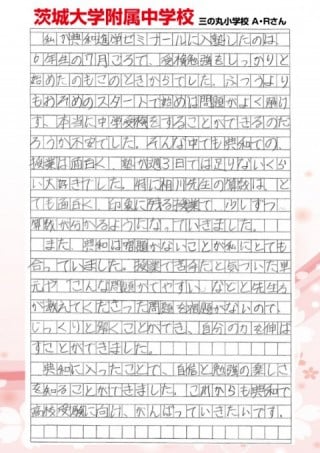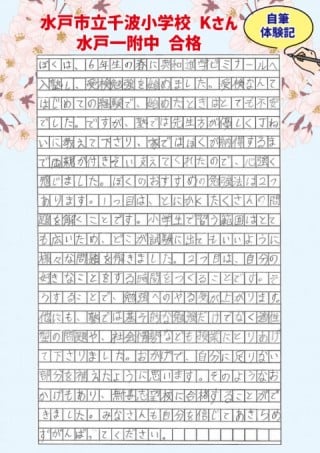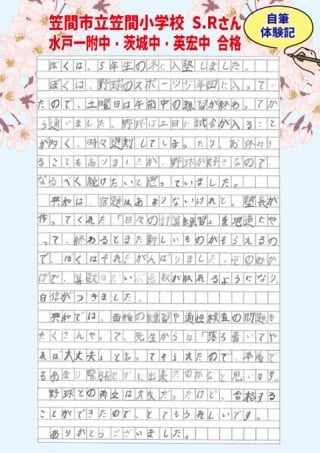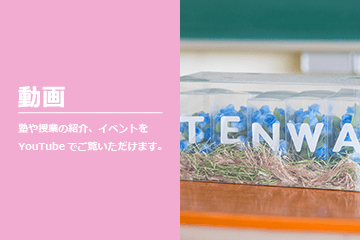典和進学ゼミナールからの「新着情報」

速報2024合格実績 国立大学
― 春から大学生になります。―
北海道大学 2名
東北大学 1名
宇都宮大学 1名
千葉大学 1名
茨城大学 2名
琉球大学 1名

― 2024春が来ました。―
私立大学合格実績
慶應 明治 東京理科大
北里 東邦 芝浦工大
東洋 東京都市 帝京
東京電機 東海 聖路加
日赤 工学院
重要なお知らせ
『典和からの電話着信表示にご注意ください!!』
典和進学ゼミナールでは、移転に伴い、電話番号を変更いたしましたが、
不具合で「パワーストーンラボ」と表示されるときがございます。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
「029-306-9371」 は当塾の電話番号となりますので、
宜しくお願い申し上げます。
「パワーストーンラボ…✘」
「典和進学ゼミナール…◎」です!!
文章(+イメージ)
2024-04-01
2024-03-13
2024-01-01
| RSS(別ウィンドウで開きます) | もっと見る |
CONTACT
お問い合わせ
お問い合わせ
ご質問やご相談など、お電話またはメールフォームにてお気軽にお寄せください。
TEL. 0120-108-314
【電話受付時間】14:30~21:00(月~土)